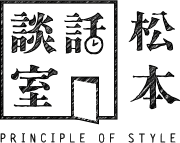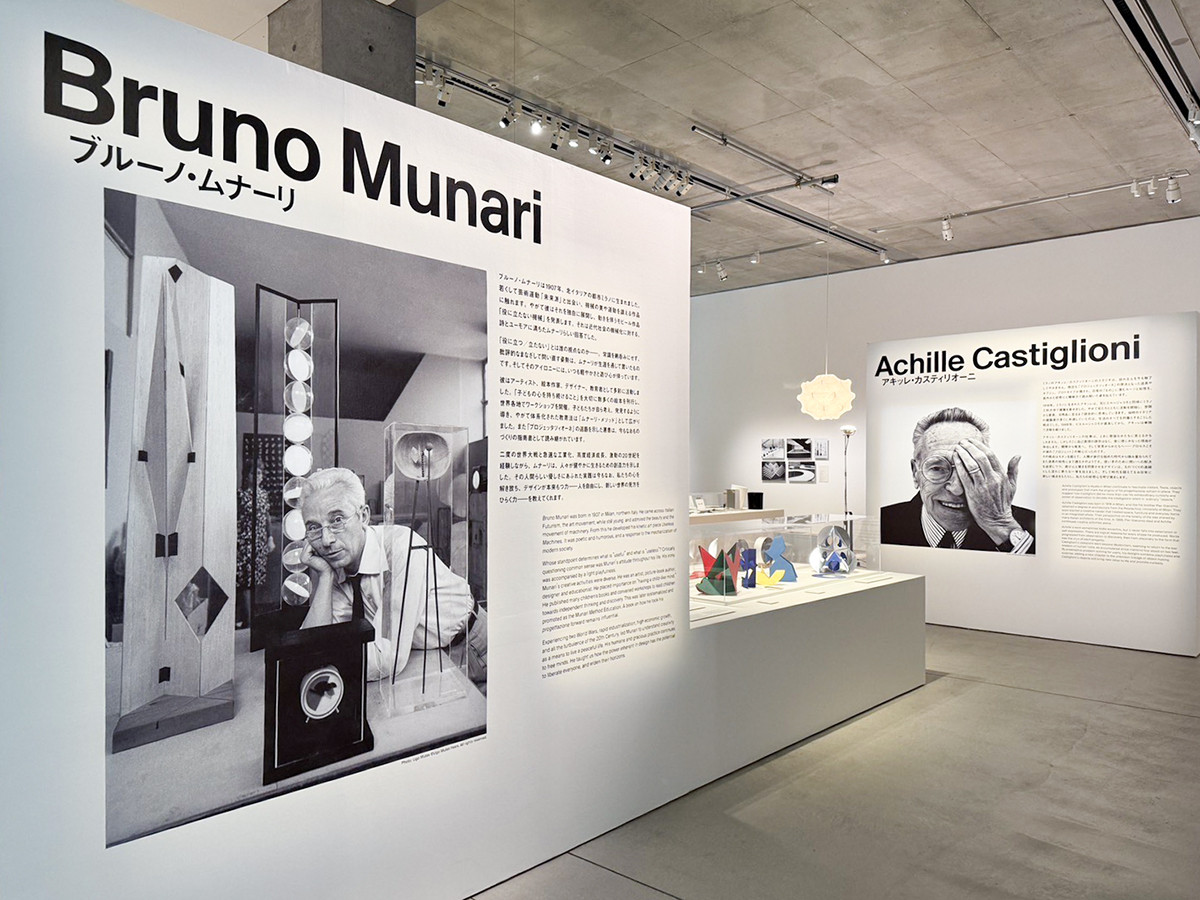東京新宿生まれ。
漫画家の父親を持ち、幼い頃より絵だけは抜群に上手かったが、
働く母の姿を見て葛藤し、美術を捨てて一般の道に進むことを決意。
しかし高校で出逢った美術の先生に熱心に説得され、再び芸術の道に。
その後、美術大学を卒業するも一般の上場企業に就職。
10年勤務ののち、またしてもクリエイティブを目指して退社独立、現在に至る。
血と芸の呪縛 国宝
Aug 13,2025
話題の映画を見てきました。
いやぁ3時間ですよ、3時間
黒澤明の「七人の侍」みたいに、昔なら途中でトイレの休憩時間が入るレベルの長さです。
こんな長い映画を映画館で見たのは久々です。
でもあっと言う間で、まったく長さは感じませんでした。
一応フィクションだと言われていますが、実在する誰かのドキュメンタリーを見ているようです。
原作の小説がありますが、きっと複数の実話を題材にしてるのじゃないでしょうか。
でないとこのリアリティは出ないのはないかと。

なぜこの映画がこんなにヒットしているのか知りたくなった
めちゃ流行っているので、皆さんの中にも見ている人は多いでしょう。
なぜこの映画がこんなにも話題になっているのか?
それを探りたいというのも自分の目的の1つでした。
20代の子たちがたくさん映画館に足を運んでいるというのも興味深いと思った理由です。
歌舞伎に興味ある20代なんてかなり少ないでしょうからね。
まぁ自分もないですけど。
なぜこの映画がこんなにも話題になっているのか?
それを探りたいというのも自分の目的の1つでした。
20代の子たちがたくさん映画館に足を運んでいるというのも興味深いと思った理由です。
歌舞伎に興味ある20代なんてかなり少ないでしょうからね。
まぁ自分もないですけど。

主演は吉沢亮
映画としてのストーリー構成、リアリティ、映像美、加えて主演2名の推し要因もかなりの集客要素になっているのじゃないでしょうか
自分の子供の同級生のママは、映画館で5回も見たという、、、、、3時間を5回だから計15時間ですよ。
映画館までの往復の時間を加えたら20時間以上かけてるわけで、、、
すごいパッション。
推し活の要素が強いのは否めません。
ただ映像美というのはあって、もちろん演者の素材の美しさがあっての映像美というのも確かにあります。
ちなみに撮影は、カンヌ国際映画祭でパルム・ドール賞受賞の経験を持つソフィアン・エル・ファニという人です。
自分の子供の同級生のママは、映画館で5回も見たという、、、、、3時間を5回だから計15時間ですよ。
映画館までの往復の時間を加えたら20時間以上かけてるわけで、、、
すごいパッション。
推し活の要素が強いのは否めません。
ただ映像美というのはあって、もちろん演者の素材の美しさがあっての映像美というのも確かにあります。
ちなみに撮影は、カンヌ国際映画祭でパルム・ドール賞受賞の経験を持つソフィアン・エル・ファニという人です。

やはり渡辺謙の演技がこの映画の核になっているように思います
自分は事前にサイトやSNSにある感想やあらすじなどは一切読まずに、ゼロベースで見たんですが、推し要素を抜いたとしても十分面白かった。
一番記憶に残ったのは、渡辺謙の演技ですね。
かなりの名演です。
このキャスティングと演技こそが、作品全体に深みを持たせる大きな役割を果たしてます。
謙さんが演じているのは、上方歌舞伎の名門「丹波屋」の花井半二郎という当主ですが、晩年糖尿病で目が見えなくなりながらも「花井白虎」という歌舞伎界の頂点に立つ大名跡を襲名します。
ところが、そのお披露目の舞台の上で、半二郎は血を吐いて亡くなってしまう。
その様子がキッスのジーン・シモンズまんまの形相で、すごく印象に残りました。。
ただこのシーンこそが、歌舞伎は「血」なのか、それとも「芸」なのかという、まさに映画「国宝」の核心を伝える重要なシーンなのです。
半二郎は最後に、舞台の上で息子の名前を連呼して亡くなります。
謙さん演じる花井半二郎の家には、一人息子の俊介と、長崎のヤクザの家から引き受けた喜久雄の2人の子供がいますが、父が後継者として最終的に指名したのは背中に大きな入れ墨の入った極道の息子である喜久雄でした。
2人は幼い頃から父親から芸の厳しい指導を受け、互いに切磋琢磨しながら育ちますが、名門「丹波屋」の後継者として半二郎が指名したのは、実の子ではない喜久雄だった。
それは半二郎が、血筋よりも芸を重んじた結果でした。
これで2人の人生は大きく狂ってしまう。
息子を厳しく突き放した半二郎が、死の間際で呼んだのは、「丹波屋」の跡を継ぐ喜久雄ではなく、既に家を出て音信不通となっていた俊介の名前でした。
そこに父親としての姿と、芸だけを追求する者との葛藤が見て取れます。
芸の技術が上だけど、実子ではない喜久雄を後継者に選ぼうとする半二郎、それを止めようとする奥さんを演じた寺島しのぶの演技もスゴくよかった。
一番記憶に残ったのは、渡辺謙の演技ですね。
かなりの名演です。
このキャスティングと演技こそが、作品全体に深みを持たせる大きな役割を果たしてます。
謙さんが演じているのは、上方歌舞伎の名門「丹波屋」の花井半二郎という当主ですが、晩年糖尿病で目が見えなくなりながらも「花井白虎」という歌舞伎界の頂点に立つ大名跡を襲名します。
ところが、そのお披露目の舞台の上で、半二郎は血を吐いて亡くなってしまう。
その様子がキッスのジーン・シモンズまんまの形相で、すごく印象に残りました。。
ただこのシーンこそが、歌舞伎は「血」なのか、それとも「芸」なのかという、まさに映画「国宝」の核心を伝える重要なシーンなのです。
半二郎は最後に、舞台の上で息子の名前を連呼して亡くなります。
謙さん演じる花井半二郎の家には、一人息子の俊介と、長崎のヤクザの家から引き受けた喜久雄の2人の子供がいますが、父が後継者として最終的に指名したのは背中に大きな入れ墨の入った極道の息子である喜久雄でした。
2人は幼い頃から父親から芸の厳しい指導を受け、互いに切磋琢磨しながら育ちますが、名門「丹波屋」の後継者として半二郎が指名したのは、実の子ではない喜久雄だった。
それは半二郎が、血筋よりも芸を重んじた結果でした。
これで2人の人生は大きく狂ってしまう。
息子を厳しく突き放した半二郎が、死の間際で呼んだのは、「丹波屋」の跡を継ぐ喜久雄ではなく、既に家を出て音信不通となっていた俊介の名前でした。
そこに父親としての姿と、芸だけを追求する者との葛藤が見て取れます。
芸の技術が上だけど、実子ではない喜久雄を後継者に選ぼうとする半二郎、それを止めようとする奥さんを演じた寺島しのぶの演技もスゴくよかった。

喜久雄の子供時代を演じた子役、怪物にも出ていたけど演技がめちゃうまい
自分はもちろん歌舞伎の家に生まれたわけではありません。
ただ漫画家の家に生まれて、この「血」と「芸」について感じることは結構ありました。
以前この談話室でも紹介しましたが、ちばてつやさんの長男が会長を務める「被害者の会」という会があって、漫画家の息子や娘たちだけが集まる(漫画家の二世以外は参加できない)会があるんですが、そこに集まるメンバーのことを想い出したり。
その会には自分も誘われて3回くらい参加したけど、手塚さんの兄妹も水木さんの娘も、赤塚不二夫さんの娘も、血の重圧から逃れられない葛藤と宿命をみんな抱えていました。
映画の「芸」にあたるマンガを描いてる子供は、二世では誰一人いないというのが、それを代弁しています。
だから「被害者の会」なのですけど、、、、笑
彼らのように売れてないながらも漫画家の父親の元に生まれ、自分も「血」と「芸」で少なからず葛藤する人生を歩んできました。
ただ漫画家の家に生まれて、この「血」と「芸」について感じることは結構ありました。
以前この談話室でも紹介しましたが、ちばてつやさんの長男が会長を務める「被害者の会」という会があって、漫画家の息子や娘たちだけが集まる(漫画家の二世以外は参加できない)会があるんですが、そこに集まるメンバーのことを想い出したり。
その会には自分も誘われて3回くらい参加したけど、手塚さんの兄妹も水木さんの娘も、赤塚不二夫さんの娘も、血の重圧から逃れられない葛藤と宿命をみんな抱えていました。
映画の「芸」にあたるマンガを描いてる子供は、二世では誰一人いないというのが、それを代弁しています。
だから「被害者の会」なのですけど、、、、笑
彼らのように売れてないながらも漫画家の父親の元に生まれ、自分も「血」と「芸」で少なからず葛藤する人生を歩んできました。

永瀬正敏の極道の親分の演技もよかった
話が少し逸れましたが、
映画の冒頭に出て来る、喜久雄の父親である極道の親分を演じる永瀬正敏のシブい演技や存在感もよかった。
タイトルが出る前のオープニングがとても印象的で、映画の前半の山場とも言えます。
歌舞伎と極道がズブズブな関係なのも、なんとも昭和らしい。
実話としか思えないです。
この映画は1964年から始まるのですが、そこから現代まで時代の変遷が的確に表現されていて、それもなかなか唸らせるものがありました。
エンドロールにVFXのスタッフがたくさん出てきましたが、昭和の空気感はセットではなく、すべてCGってことなのかなぁ
すごく良くできてましたね。
あとは三浦友和の息子の演技力も光ってました。
嶋田久作演じる歌舞伎に出資する社長の息子を演じてますが、最後まで歌舞伎に関わり、歌舞伎業界と喜久雄をつなぐ重要な役どころ。
この人地味なのに存在感があり、父親の友和より演技が光ってました。
そして兄ちゃんよりも才能あるかも。
最後に、人間国宝の歌舞伎役者を演じる田中泯の異様な存在も忘れられないですね。
見た後に国宝というタイトルは、人間国宝のことを言っているんだということに気づかされます。
国宝とは美術品ではなく、生身の人間が表現する芸術。
その意味では、目には見えているけれど、そこに隠された継承や精神のことを指しているのかもしれないということに気づきます。
それを喜久雄という(架空の、あるいは現実の)存在に表現させているという作品です。
映画の冒頭に出て来る、喜久雄の父親である極道の親分を演じる永瀬正敏のシブい演技や存在感もよかった。
タイトルが出る前のオープニングがとても印象的で、映画の前半の山場とも言えます。
歌舞伎と極道がズブズブな関係なのも、なんとも昭和らしい。
実話としか思えないです。
この映画は1964年から始まるのですが、そこから現代まで時代の変遷が的確に表現されていて、それもなかなか唸らせるものがありました。
エンドロールにVFXのスタッフがたくさん出てきましたが、昭和の空気感はセットではなく、すべてCGってことなのかなぁ
すごく良くできてましたね。
あとは三浦友和の息子の演技力も光ってました。
嶋田久作演じる歌舞伎に出資する社長の息子を演じてますが、最後まで歌舞伎に関わり、歌舞伎業界と喜久雄をつなぐ重要な役どころ。
この人地味なのに存在感があり、父親の友和より演技が光ってました。
そして兄ちゃんよりも才能あるかも。
最後に、人間国宝の歌舞伎役者を演じる田中泯の異様な存在も忘れられないですね。
見た後に国宝というタイトルは、人間国宝のことを言っているんだということに気づかされます。
国宝とは美術品ではなく、生身の人間が表現する芸術。
その意味では、目には見えているけれど、そこに隠された継承や精神のことを指しているのかもしれないということに気づきます。
それを喜久雄という(架空の、あるいは現実の)存在に表現させているという作品です。

坊ちゃんと極道の子の差異がうまく表現されていた
ということで
吉沢亮、横浜流星の2人についてまったく触れませんでしたが、2人への共感を求めていた人にとって、このテキストを読むこと自体まったくの無駄な時間になってしまったかと思いますw
スミマセン・・・・
映画の中で、坊ちゃんである横浜流星と、極道の息子である吉沢亮、2人の描かれ方がちょっとした仕草、着ている洋服や髪形などに現れていて、うまく表現されていました。
吊り橋の上での2人のシーンがよく出てきますが、調べてみたら大阪にある玉手橋という橋だそうで、昭和4年(1929年)に建造されて今も使われているようです。
とてもクラシックでカッコいい橋ですね
と、、また2名と関係ない話を。
吉沢亮、横浜流星の2人についてまったく触れませんでしたが、2人への共感を求めていた人にとって、このテキストを読むこと自体まったくの無駄な時間になってしまったかと思いますw
スミマセン・・・・
映画の中で、坊ちゃんである横浜流星と、極道の息子である吉沢亮、2人の描かれ方がちょっとした仕草、着ている洋服や髪形などに現れていて、うまく表現されていました。
吊り橋の上での2人のシーンがよく出てきますが、調べてみたら大阪にある玉手橋という橋だそうで、昭和4年(1929年)に建造されて今も使われているようです。
とてもクラシックでカッコいい橋ですね
と、、また2名と関係ない話を。

話題性とのギャップ、深いテーマの映画でした
3時間という長い映画ですが、見て損はありません。
2人の推し活としてだけでなく、血と芸というテーマを切り口にした伝統芸能の深さ、継承の重圧、人間の業も感じさせる、やっぱり色々考えさせられる映画です。
美しいというより、いや美しい世界だから奥が深いというべきか。
20代の人たちが、これを見てどう感じたのか聞いてみたくなりました。
皆さんも映画館へ是非。
感想教えて欲しいです。
2人の推し活としてだけでなく、血と芸というテーマを切り口にした伝統芸能の深さ、継承の重圧、人間の業も感じさせる、やっぱり色々考えさせられる映画です。
美しいというより、いや美しい世界だから奥が深いというべきか。
20代の人たちが、これを見てどう感じたのか聞いてみたくなりました。
皆さんも映画館へ是非。
感想教えて欲しいです。